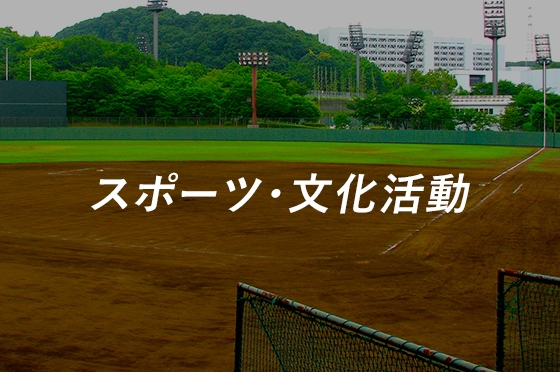2025.03.31
「人のワクワクに貢献できる仕事に就く」
「ガクチカ―強い思いを持って何かに取り組む」
「若手のうちからバリバリ働き、実力で生きていく」
女子学生の就活応援でセミナー開催
- キャリア
- きょう・あした
女子学生の就職活動を支援する第30回WINGの会「女子学生応援セミナー」が2024年11月30日、茗荷谷キャンパスを主会場に対面とオンラインで開催された。内定を取得した4年生の女子学生3人がパネルディスカッションに登壇し、就活体験から感じ、考えたことなどを1~3年生の参加者に語りかけたほか、卒業生で東京都職員の白田奈美さん(2015年法学部卒)が「本当の自分に合ったキャリアプランを考える」と題して講演した。
セミナーは卒業生でつくる学員会の女性支部「女性白門会」とキャリアセンターが共催した。WINGの会は女性の卒業生から現役学生に対する進路・就職活動への応援を目的に発足した。また、学生記者4人がセミナーを聴講し、考察したことを記した。
パネリストを務めた内定者の4年生3人
ディスカッションでパネリストを務めたのは、法学部4年の山田菜月さん(内定先・本田技研工業)、文学部4年の疋田(ひきた)茉衣さん(内定先・東京都)、経済学部4年の八森(はつもり)舞さん(内定先・アビームコンサルティング)の3人。就活をめぐるテーマ別に次のように説明、回答した。
【質問 就活の軸、就活で大切にしていたことは何ですか】
山田菜月さん 人々のワクワクに貢献できる仕事(に就くこと)です。一生懸命に取り組めたことのモチベーションを考えたとき、自分と周りの人にワクワクを届けられることがやりがい、喜びにつながっていました。自動車を通して、楽しい思い出や人との絆が深まるようにしていきたいという思いがあります。
疋田茉衣さん 一度入った組織で長く勤めたいと思っていました。平均勤続年数の長い企業や業界です。私は「絶対にこれがやりたい」ということはなく、「いろいろなことをしたい」「幅広い業務に携われる仕事がいい」と思っていました。
八森舞さん 将来はサラリーマンを辞めて自営をするという夢があるので、若手のうちからバリバリ働き、力をつけないとだめだと思っていました。できれば年功序列でなく、実力で生きていけるようなところがいいなと思い、そこは大切にしていました。
【質問 メンタルの維持や気分転換はどうしていましたか】
山田さん 気分転換していても、就活を思いだしてブルーになるということがありました。自信をつけようと思って、キャリアセンターなど頼れるものは全部頼って対策をして、自分の中に自信を積み重ねて不安と向き合っていました。
疋田さん 勉強が苦手で1次試験に通るかが不安でした。「私は公務員に向いている」「私ほど向いている人はいない」と自己暗示をかけました。どうしてもしんどいときは、勇気をもって一日休んで遊びに行きました。
八森さん 就活から離れる。就活の話題だけで疲れるので、違う話をする、普通に楽しむことをしました。サマーインターンに落ちて辛かったときは、「落とす企業が悪い。私は悪くない」という気持ちでやっていました。
山田菜月さん
疋田茉衣さん
八森舞さん
【質問 就活前までにやっておいた方がよいことは何ですか】
山田さん 学生時代に「何を」「なぜ「どのように」続けられたかという部分、その中でどう自分らしさを出したのかという「what」「why」「how」を(会社側に)重視されていたと思います。自分の中で目的意識をもって主体的に取り組んだというエピソードを作っておくと大きな武器になるでしょう。
疋田さん 「ガクチカ」を書くためにいろいろなことをやってほしい。強い思いを持って何かに取り組むと書きやすいと思います。公務員は、これまでに勉強してきたことを面接カードに書く必要があるので、学業もしっかりやってほしいです。
八森さん 学生時代を全力で楽しむ、打ち込むことです。「ガクチカ」を自信をもって書けるくらい楽しんだり、打ち込んできたりしたことがあったら、すらすらと書けます。それを意識しないで過ごすと、苦労します。こういうことに力を入れたと語れるエピソードを作ってほしいと思います。
法学部卒業生で東京都職員の白田奈美さんは講演で、都庁における女性の働きやすさなどを、自身の経験や豊富なデータをもとに語りかけた。家庭を持った場合の夫婦の就業パターン別に、家庭の生涯収入の試算額などを示したほか、就職先の選択とともに、管理職を希望するかどうかといったキャリアプランについても、社会人の話を聞いた上でイメージを膨らませ、自らの将来を考えてほしいと呼びかけた。
セミナーの結びには、進行役を務めたキャリアセンター職員が、「ガクチカは学生時代の成果を書くと勘違いする人がいますけれど、(チームの中で)自分がどのようにふるまって、どう成長したかが大事です。就活のためと思うと重いかもしれないけれど、せっかくの大学生活を楽しんでほしい」とメッセージを送った。
第30回WINGの会 女子学生応援セミナー

白田奈美さん
〈日時〉2024 年11月30日14:00~16:50
〈主会場〉茗荷谷キャンパス(対面・オンラインで開催)
【第1部】卒業生による講演
「本当の自分に合ったキャリアプランを考える」
登壇者:東京都職員 白田奈美さん
〈略歴〉法学部法律学科2015年卒、同年東京都庁に入都。障害者施策推進部障害者支援施設・社会参加推進担当、保健政策部難病認定担当を経て、2023年4月より、現在の保健政策部国民健康保険課国民健康保険事業会計担当主事。
【第2部】内定者パネルディスカッション
「今、知りたい就活のリアル!~就活経験者が語る本音の60分」
パネリスト
法学部4年 山田菜月さん(内定先・本田技研工業)
文学部4年 疋田茉衣さん(内定先・東京都)
経済学部4年 八森舞さん(内定先・アビームコンサルティング)
〈共催〉
中央大学学員会女性白門会
中央大学キャリアセンター
東京都職員で卒業生の白田奈美さんによる講演
〈取材後記〉「キャリアとは人生そのものである」
学生記者 近藤陽太(経済4)
セミナーを通して、キャリアとは単に昇進の階段を上ることではなく、人生そのものであるという学びを得ることができた。
特に印象に残っているのは、東京都職員である白田奈美さんの「都庁人生を考えたときに必ずしも上のポジションに立つことがすべてではない」という言葉だ。白田さんは、最も働きがいを感じるポジションで働くことが大切だと話した。出世を目指すことが自分のキャリアの目標であると考えていた私には、その考え方が新鮮だった。
パネルディスカッションでは、一つの企業で長く働き続けたいという人や、将来的に独立を考えている人など、それぞれが異なるキャリアプランを描いており、多様な生き方があることを実感した。女性だけではなく、すべての人が自分にあったキャリアを選べることが重要であると学んだ。2025年から社会人になる私も、これからのキャリアをあせらずに考え、自分らしく生きていきたいと思っている。
セミナーでは就活の“コツ”も話題に上った。就活を終えた私の目線で共感したのは、白田さんの「社会人として経験している方の話を聞いてイメージを膨らませる」という話だ。「社会人として経験している方」には2種類あると考えられる。
一つは、親や先生などの身近な大人。あなたの性格を理解した上で相談に乗ってくれる貴重な存在だし、つらいときに寄り添ってもくれるだろう。もう一つは就活で出会う企業の大人だ。その企業でのキャリアの歩み方をその人自身の経験を踏まえて話してくれるので、より深く業界や企業について知ることができるだろう。
私自身、就活で感じたことは「直接会う」ことの重要性だ。就活でもオンライン化は進んだが、ぜひ直接、働く人の生の声を聞いてほしいと思う。リアルな対話を通して、働く人の雰囲気を肌で感じることができる。企業とのマッチングともいわれる就活を楽に進めるには直接、企業の人と会うことが有用であるように思う。
就活に行き詰まる時期は誰にもある。私も3年生の冬に「何もやる気が起きません」とキャリアセンターに相談した経験がある。就活を乗り切るため周囲を頼るのも策だ。そういう意味でも就活は人との関わりなのではないだろうか。
〈取材後記〉企業選択の具体的着眼点を学ぶ
学生記者 九十歩胡春(文1)
法学部卒業生で東京都職員の白田奈美さんの講演から、業務の忙しさとともに、充実した職場環境もうかがえた。「継続して働きやすい」「安定している」というイメージが公務員志望の理由と話された一方で、人事異動が数年おきにあることや、業務の多様さを知り、刺激的な日々を送っていることがわかった。
白田さんが都庁で働き始めた頃、障害者支援施設担当だったときのエピソードが印象に残っている。「国の基準を満たし、補助金がもらえればいい」とだけ考えている施設と、利用する障害者のことを本当に考えている施設が存在したという。実際に障害者や施設職員と真摯に向き合わないと知ることのできない現実であり、東京都という大規模自治体であっても、人と一対一で接する仕事であると知ることができた。
入庁3年目の社会参加推進担当だったときは、電車の優先席付近などに貼る「ヘルプマーク」のステッカー普及の仕事に携わり、自らの努力もあって普及が進んだことにやりがいを見いだしたというエピソードも素敵だと感じられた。
内定を得た4年生によるパネルディスカッションは有益な情報ばかりだった。企業選択の基準として、興味ある分野かどうか、給与や労働時間、休日日数くらいしか、私はすぐには思い浮かばなかったが、勤続年数や産休・育休制度の詳細と取得状況、組織の上層部に占める女性の割合、転勤の有無や頻度といった具体的な着眼点を聞くことができ学びになった。
セミナーを通して、就活は想像していた以上に大変そう、忙しそうという印象を受けたものの、パネリストの4年生の方々が笑顔で話しかける様子も心に残った。「どうせやらないといけないなら早めにやろう」「面接は会話を楽しむ」「就活を楽しむ」「勇気を持って一日休んで遊ぶ」「自分ほどこの仕事に合う人はいないと自己暗示をかける」といったポジティブな言葉の数々から、体力勝負であるとともに、メンタルを保つ大切さも学んだ。
就活を始めるまでに、就活にとらわれ過ぎないようにしつつも、何か熱中して努力したといえる経験を積みたいと思っている。
(写真左から)パネリストの山田菜月さん、疋田茉衣さん、八森舞さん
〈取材後記〉「目的を持って主体的に行動する」ことの大切さ
学生記者 金岡千聖(商2)
パネリストの先輩が話された「就活自体を楽しむ」という考え方に感動し、就活に対する考え方がポジティブな方向へと大きく変わった。就活を自分の人生を決める大事なイベントだと捉え、非常に重く感じていたが、先輩方は「就活は将来を決められる素敵な機会」とたとえていた。
就活に対する私のイメージは「一人ですべてをこなし、一人で戦っていく」だった。キャリアセンターは静かで緊張してしまい、足を運びづらいという勝手なイメージがあったが、多くの学生が相談に訪れていると聞き、気軽に頼れる場所があることに安心できた。
講演した東京都職員の白田奈美さんは、実際に職員(社員)に話を聞く方が、職場の実状が分かると話した。現実に働いている人の話を聞くことは、その職場や組織が果たして自分に合うのかどうかを判断する重要な材料になるだろう。
また、女性として、妊娠や子育てに関する話も興味深かった。特に、都庁には私の知らないさまざまな制度があり、感心した。育休に関しては、女性職員の育休の取得率を尋ねるより、むしろ男性職員の取得率を聞いた方が、制度がその組織でどの程度理解され、浸透しているかが分かるという分析には、ハッとするものがあった。
パネルディスカッションでは、「ガクチカ」について、特別なことを書かなくてもよいという話が出た。私も胸を張れるようなすごいガクチカのエピソードがないとあせっていたが、どのような体験でもしっかりと取り組めば、自分の成長や頑張りを訴えることができると気付き、「目的を持って主体的に行動すること」が重要だと学んだ。
この気づきは、今後の学生生活でも目的意識を持った行動を心がけようとする姿勢につながると思う。就活の真の意義は、自分の将来のキャリアについて真剣に考えることにあるだろう。セミナーで聞いたことを生かして、私も学業と両立しながら就活を順調に進め、後悔のない選択をしたいと思っている。
〈取材後記〉就活を前向きに捉える「女性ならではの視点」が刺激に
学生記者 木村結(法2)
漠然とした不安を抱えていた就職活動を前向きに捉えることができるようになったセミナーだった。同じ女性ならではの視点の話もうかがえて、良い刺激となった。
就活のためだけに学生生活があるわけではないが、学生生活の全てが就活につながると強く感じた。自分が行う活動を目的意識を持って取り組むことが、就活にも生かされることを学んだ。就活のため、何か特別なことをしようと意気込む必要はなく、大学生活の延長線上に就活がある。今までやってきたことに胸を張って、就活すべきだと考えを改めた。
卒業生で東京都職員の白田奈美さんの講演は、実務に関することからプライベートな内容まで貴重な話を聞けて興味深かった。就職後の職場環境や、ライフステージが移ろう中で変化する家庭の状況などにイメージが膨らむような内容だった。
東京都に女性が働きやすい環境や、長く働ける条件が整っていることを紹介され、魅力を感じた。民間も見習うべきところがあるなら見習ってほしいと思った。白田さんは、あえて管理職を目指さなくてもよいとも語った。自分がなりたい将来像に合わせて、自分の価値観でキャリアプランを考えていくことの重要性を感じた。
4年生3人のパネルディスカッションで、年の近い先輩方の話を聞き、やるべきことが明確になった気がする。3人ともさまざまな軸や目標で就活と向き合い、強い信念をもって活動していたことに感銘を受けた。
一番印象に残ったのは、同じ法学部の山田菜月さんの話だ。産休や育休などライフステージが変化しても仕事を続けられるかについて、実際に働く社員に質問し、確かめたという。家庭との両立のため、不可欠で大事な観点の一つだと気づかされた。
今回のセミナーを通して、就活は収入を得て生きていくための社会人としての一歩であり、選択肢の幅を広げながら取り組むことが必要だと考えた。私自身の強みを生かして、自分の描く将来像とキャリアプランを軸に、未来に向けて就職活動を行っていきたい。