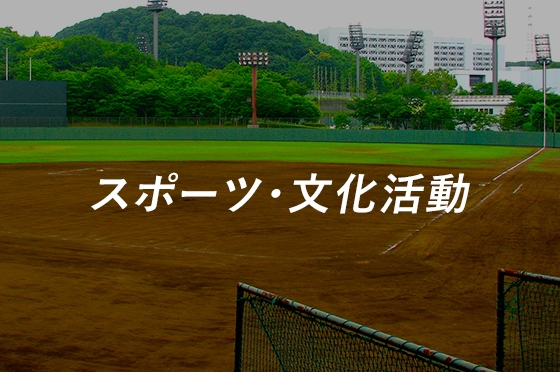2024.12.13
IT産業の集積地 ベンガルールで商習慣、文化を知り、学ぶ
インドのスタートアップ企業、日系企業でインターン体験
理工学部、国際経営学部 学生4人の報告
- 中大ニュース
- キャリア
理工学部の設置科目「グローバル・インターンシップ」(担当:藤井真也特任教授)と、国際経営学部の設置科目「インターンシップ」(担当:国松麻季教授)で学んでいる学部生10人(理工4人、国際経営6人)が夏休み期間の8~9月、「インドのシリコンバレー」といわれる南部の都市、ベンガルールを拠点とするスタートアップ企業、日系企業で、インターンとして仕事に従事しました。
1カ月の経験を自身の貴重な財産として帰国した10人のうち、理工学部1年の大川真利奈さんと野口叶夢(かなめ)さん、国際経営学部3年の棚橋里緒さん、同2年の飯野桜太(おうた)さんの4人に、インターンの仕事を通じて得た学びや、今後の糧となったこと、日本との商習慣の違い、交流したインドの人々の気質や特長、国柄などについて話を聞きました。
REPORT # 1
「起業してずっとインドとつながりたい」
理工学部1年 大川真利奈さん/派遣先:Rakuten India Enterprise Private Limited

インターンの修了証書を受け取った大川真利奈さん(左)
広告システム全体を統括する「Global Ad Technology Department(GATD)」という部門に所属し、自社開発アプリなどのワイヤーフレーム(サイト設計図、画面デザイン)について、使い勝手の良さを追求する仕事に携わりました。
日本企業で8年間、勤務経験のあるインド人のプロダクトマネジャーをメンター(指導・助言者)として、ワイヤーフレームを作り、どのようなサービスがユーザーに受け入れられるのかを、試行錯誤しながら取り組みました。仕事の過程で疑問に思ったことにすぐに回答してくれる、高い専門性を持った社員からも良い学びを得られました。
聞き取りづらかった英語も1~2週間で理解できるようになり、インターン期間をより有意義に過ごそうと心がけたのは「迷ったら尋ねる」「ためらわずに聞く」ということ。ロゴや写真などサイトを構成する素材を渡され、「ワイヤーフレームを作って」と最初に指示されたときは「困ったな」と思いましたが、「試行錯誤しながら何とかする」ことも大事だと気づきました。
「迷ったら尋ねる」「試行錯誤して何とかする」
もう一つ大切に感じたのは、長い時間を過ごす場所である職場の環境です。Rakuten India では社屋各階にソファが置かれ、コーヒーや菓子で一息つける場所、仮眠可能な場所、ビリヤードなどができる遊びの空間、ジムも併設されていました。休憩したいときに休憩できるという感じで、働いている皆さんはとても楽しそうな雰囲気でした。
私は以前から「インドに行ってみたい」「起業したい」という思いを抱き、インドに留学経験のある日本人の起業家から「人生が変わる」と勧められて参加しました。平均年齢が若く、熱気にあふれた国であることを肌で感じ、人口も多く、日本以上にハングリー精神に満ちた競争社会という印象を受けました。しかし、競争はあっても、インド人は人と人の結びつきを大切にする親切で優しい人たちです。
充実した1カ月を過ごした今回の経験があって、起業意欲はますます高まりました。AI(人工知能)エンジニアとして、インドの人たちとずっとつながれるような事業に携わりたい。インドの人に日本をもっと好きになってもらえるような起業、たとえば観光に関する起業を手がけたいと考えています。


REPORT # 2
インド的思考「躊躇するな」 会話に割り込む「度胸」つく
理工学部1年 野口叶夢さん/派遣先:Rakuten India Enterprise Private Limited

インターンの総括プレゼンテーションを行う野口叶夢さん
当初2週間はプロダクトマーケティングチーム、後半はマネジメントチームに所属し、チームの業務の全体像の把握と、電子メールによるマーケティングの手伝いなどを担当しました。
将来の就活も考慮に入れ、エンジニアの数が米シリコンバレーを上回るベンガルールのIT 企業ということで参加しましたが、一番に学んだのは社会人としてのコミュニケーションの仕方やマナーのほか、企業にはそれぞれ共有する価値観や文化があるということです。
Rakuten India の社員千数百人の99%はインド人でしたが、「常に改善、常に前進」「スピード!! スピード!! スピード!! 」といった日本と同じ「楽天主義」に基づくコンセプトが浸透していました。私のメンターも「プッシュ、プッシュ、プッシュ!」とスピード感を高めて仕事をするよう、声をかけてきたことを覚えています。契約を増やすという課題のプレゼンテーションで解決案を評価されたときは、やりがいを感じました。
意見をはっきりと口にするようになる
インド的な考え方ではないかと感じた印象に残るエピソードを紹介します。
メンターは非常に多忙な方でしたが、「朝夕に5分間、2人でミーティングをしよう」と言葉をかけてくれていました。ところが、他の社員との会話が途切れずに、話せない場面が頻繁にありました。
会話をさえぎって割り込んでいくのは度胸が要り、日本人の感覚からすると躊躇(ちゅうちょ)してしまうところです。しかし、メンターは「何よりも自分の時間を大切にしないといけない」「躊躇するな」と何度も言ってくれました。
おかげで、以前より自分の意見をはっきりと口にできるようになりました。場の空気を読むことの多い日本にどこか息苦しさを感じるような人にとって、インド社会は居心地が良いかもしれません。
インターンとして働くこと、英語を使って働くことなど、何もかもが初めてで、将来海外で働くことを視野に入れたとき、外国人とのコミュニケーションや、相手の文化を知る大切さに気づかせてくれた貴重な経験でした。日本での就職を考えれば、国内の企業でもインターンとして働いてみたい。就活には、データサイエンスやプログラミングの知識をさらにつけて臨みたいと考えています。

会社の休日ボランティアで木を植える活動をしたときの一枚(右端が野口さん)
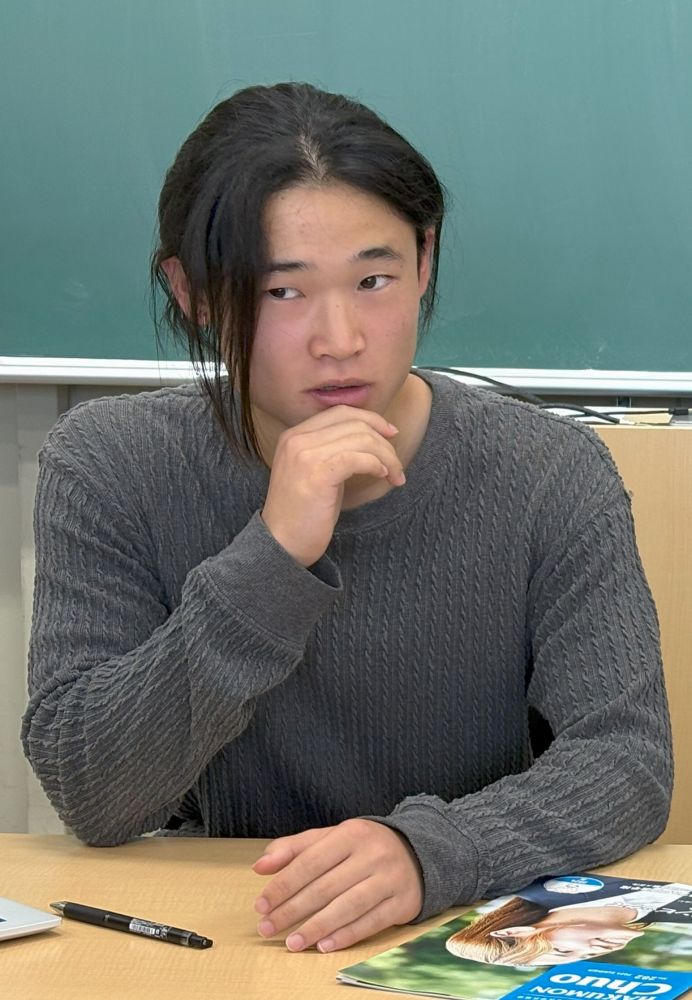
REPORT # 3
インド企業のスピード感 「その場で試行錯誤、失敗なら即改善」
国際経営学部3年 棚橋里緒さん/派遣先:Mylin

オフィスで同僚たちと(右から2人目が棚橋里緒さん)
AIを活用した技術を他企業に提供するMylin(メイリン)のマーケティング部署で、動画配信サービスに活用できる技術を他国の企業に売り込む仕事を担当しました。従業員44人と小規模ですが、技術力に定評があり、信頼度の高い会社でした。
たとえば、サッカーの試合のインターネット配信で、回線速度の比較的遅いインドネシアでも高画質の映像を視聴可能とするような技術力です。私の売り込み先もインドネシアをはじめとする国の動画配信企業でした。もちろん、国によって人気のある動画は異なるため、それぞれの市場に適した戦略、アプローチの重要性も学べました。
フレンドリーな職場で、初日から、疑問に思ったことを何でも聞きやすい環境でした。英語でのコミュニケーションは、IT企業独自の難しいビジネス用語もありましたが、私は以前に6年半の米国滞在経験があり、ほとんど問題はなかったです。
英語力生かし、海外で働く
何か新しいことに挑戦するとき、「計画を練りに練る」という日本企業が多いのに対し、インドは「やってみて、その場で試行錯誤を重ねる。失敗したら改善する」というスタイルです。何よりスピード感に違いがあると感じました。
インターンの最終プレゼンテーションに向けて、ネット上の他国の市場調査がうまくいかずに悩んでいたところ、メンターのアドバイスで乗り切り、帰国後にオンラインで社長ら現地の幹部を前にプレゼンを実施できました。一からマーケティング戦略を立案し、やり遂げることができたため、非常にやりがいを感じたのを覚えています。
日本のような「おはようございます」「おつかれさまでした」といった挨拶の習慣がない会社だったので、私が挨拶を欠かさずにいると「すごく礼儀正しいね」と逆に驚かれました。でも、会う人は皆、優しくフレンドリーで、インドの人々には親しみを感じています。
強みである英語を生かして海外で働くというのが、高校生の頃からの私の夢でした。帰国後に就活を始めたのですが、もう一度海外へインターンに行きたいとも考えています。急成長の国のビジネスの現場を実際に感じられるところがインドの魅力だと思います。

夜のベンガルールの街の様子

レストランのインド料理

ベンガルールを走る鉄道
REPORT # 4
意見をぶつけ合うことで生み出す価値
国際経営学部2年 飯野桜太さん/派遣先:Yulu

チームメンバーと休憩中に撮影(右端が飯野桜太さん)
Yulu(ユル)はレンタルの小型バイクを提供する2019年設立のスタートアップ企業で、急成長を遂げています。私は約60人が働くビジネスチームの所属でした。現地で需要の大きい小型バイクを置く街中の場所(ステーション)の提案を行うなど、国際経営学部の授業で学んだ理念を実践できる面白い仕事と感じました。
一番の収穫はインド人のマインドセット(心構え)を学べたことです。国民性や価値観が日本とは違う。「私がやっている」という意識が強く、自分の能力や仕事にプライドを持っていて、積極性やハングリーさを感じました。自分の意見を強く持っているので、ぶつけ合うことで、生みだせる大切な何かがあるんです。
働き始めて2週間後、ビジネスチームのリーダーとステーションの設置場所で押さえるべきポイントの議論になった際、「それは違う」と主張するリーダーに対し、「でも日本ならこうしている」と繰り返し反論すると、「それは良い視点だ」と反応が変わっていきました。相手の意見を必要以上に尊重しがちだった私も「やるしかない」というマインドの大切さに気付き、自分を主張する度胸がついたように思います。
ビジネスライクな雰囲気の職場で、最初はなじめるか不安もありましたが、週2回のプレゼンテーションの場で、私への質問やリアクションが増えてきたとき、上司や仲間にメンバーとして認められたと、やりがいを覚えました。
トライアンドエラー
「動いてダメなら、またそこで考える」
インド人で50歳代のYulu創設者は、東大大学院で学んだ経験があるという凄腕のビジネスマンでした。「日本人は考えすぎる。まず動いてダメなら、そこでまた考えればいい」という考えで、急成長するビジネスシーンの波に乗り遅れないよう、トライアンドエラーで取り組む姿勢が不可欠とみていたのでしょう。
学生のうちに起業したいと考えている私に、「日本で同じ起業をするなら50台貸すよ」と即座に答えてくれるなど、起業家としてスケールが大きい人でした。
「思ったことを包み隠さずに話してくれる」というインド人の人柄が好きになったと同時に、起業意欲もさらに高まりました。マレーシア、シンガポールなど伸びている国や地域のビジネスを知るため、中大在学中に海外であと一度はインターンとして働きたい。
私は海外に行くのも初めてでしたが、日本人にない新しい価値観を知りたい人に、インドはうってつけの国だと思います。

Yuluの受付
中央大学のグローバル・アントレプレナーショップ教育
世界最大の人口を有するインドにおける最大のIT 産業の集積地で、学生たちが1カ月間暮らし、仕事に携わる中で、日本と異なる特有の商習慣や文化を知り、イノベーション創出に結びつくアントレプレナーシップ(起業や新たな価値を生み出していく思考や姿勢)を培ってもらうのが、今回のインターンシップの狙い。将来の日印協力を担う人材輩出に資する目的もある。
派遣期間は2024年8月16日~9月17日。インド政府、企業の協力で実施され、派遣前に駐日インド大使館で行われた壮行会で、学生たちはシビ・ジョージ大使から激励を受けた。今後も春休み、夏休みの長期休暇を活用し、年2回実施する予定。文部科学省が推進するアントレプレナーシップ教育の一環でもある。
★ベンガルール
インド南部のデカン高原にあり、IT 大国であるインド最大のIT 産業の集積都市。都市圏人口は約1200 万人。インターン生が滞在
した8~9月は日本のような蒸し暑さもなく、避暑地のような気候で過ごしやすかったという。
★スタートアップ企業
革新的なアイデアやイノベーションにより社会に変化をもたらし、創業から数年で急成長する企業のこと。