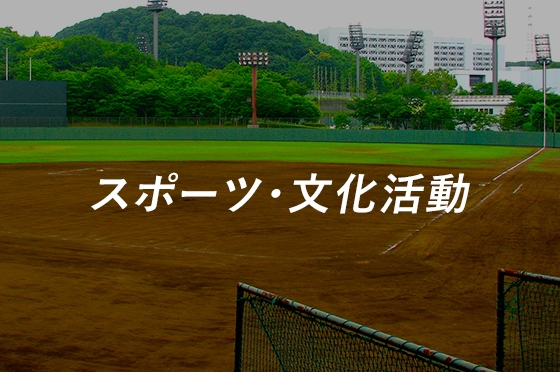2025.07.29
全日本学生落語選手権 策伝大賞で敢闘賞
「扇家なん輔」人生“最上級”に緊張した高座
落語研究会 板垣空さん(法4)
学生記者 合志瑠夏( 経済4) 荒田智海( 文2)
- 中大ニュース
- ゼミ・サークル
落語研究会(落研)の板垣空さん(法4、高座名・扇家なん輔)が、2025年2月の第22回全日本学生落語選手権(策伝大賞)決勝大会に出場、敢闘賞を受賞した。策伝大賞の歴史の中で、中大落研の決勝大会出場者は6人目(延べ8回目)という快挙。予選と決勝で披露した演目「擬宝珠(ぎぼし)」(古典落語)は、噺(はなし)の内容や言い回し、アイデアなどを自身でひねり出し、大胆にアレンジした。決勝の高座では、これまでにない「人生で“最上級”の緊張感を味わった」と振り返っている。
3度目の挑戦、初の決勝のステージへ

擬宝珠を演じる板垣空さん=2025年2月15日、岐阜市民会館
「高座以外で何十人もの人が黙って耳を傾け、見てくれるという機会は僕にはない。こんなに自己中心的になれることもない」
中央大学で落語の世界を知った。偶然のめぐり合いがきっかけだ。入学直後の6月のある日の夜、入りたいと思うサークルを探そうと、多摩キャンパスの4号館(サークル棟)を友達と一緒に歩いていた。たまたま明かりがついていて、ノックして入った部屋が落語研究会だった。
落語は「趣味」とたとえる。「実社会に出て何かに役立つかというと…。基本はあまり役立たない」と今は捉えているが、「落語を通じて(他の大学の決勝出場者を含めて)仲間が大勢できた。(策伝大賞では)尋常ではない数の方々にお世話になった。たくさん祝福されて、正直何を言われたか、よく覚えていないくらいです」と大会を思い返し、周囲に感謝する。
予選に出場した大学1年時は決勝に残れず、2年では動画審査を通過できず予選出場を果たせなかった。今回が3度目のチャレンジだった。
「恥ずかしがらずに」演じ切る
自己評価は「50点」と辛口
策伝大賞の演目「擬宝珠(ぎぼし)」は、塔のてっぺんの金属の装飾をなめるのが大好きという風変わりな嗜好(しこう)を持つ主人公「若旦那」と父親の「大旦那」のユーモアあふれるストーリー。場面、場面でひざ立ちをしたり、寝転がったりして、大きな動きや所作で演じた。せりふの言い回しやアイデアは「電車に乗っているとき思いつくことが多い」と話す。擬宝珠は台本作りに3、4カ月を要し、2024年12月の落研主催の落語会で初披露した。
塔のてっぺんの相輪(擬宝珠)をペロペロと舌でなめ回す様子や、塔によじ登り、最後は落ちて地上に戻る姿を「とにかく恥ずかしがらずに演じること」に、予選も決勝も神経をそそいだ。そのために「何も考えずにやる」と決めて挑み、そして見事に客席を笑いで満たした。
まくら(噺の導入部分)も本編も、せりふを飛ばさずにできたことに満足感を覚えながら、それでも自己評価は「50点」と手厳しい。足りなかったところを尋ねると、「緊張すると陥りがちなのですが、滑舌が悪かった。(演目後半には)汗で前髪が下りてきたので、もっとしっかりセットしておけばよかった」と反省を口にした。実は、前日の予選でも滑舌は芳しくなかった。「予選通過できたのは幸運で、びっくりした」と振り返るほどだった。

インタビューに答える板垣空さん

「落語家ぶらない」「名乗りの声を大きく」
中大落研出身の師匠からアドバイスも
古典落語をベースに、オリジナルのせりふや設定、登場人物などを創出し、アレンジしていく手法を、自身の落語の特長だと思っている。「自分で考えたネタなので覚えやすい」という。「(本職の)落語家ではないから、落語家ぶらない。奇をてらったような話し方はしない。最初の名乗りの声を大きくする」とも心がけている。
高座を何度経験しても舞台上では緊張する。お客の反応にもよるが、本編の噺が進むうちに緊張はだんだん解けていく。ただ、緊張を解くコツは「ないので緊張するんです」と打ち明けた。きっと高座を経験した人でないと分からない感覚なのだろう。
中大落研では、「ネタ見せ」の際に部員同士で指導を行うほか、年1~2回、落研出身の三代目桂やまと師匠、春風亭三朝師匠らから指導を受ける機会がある。板垣さん自身、「大きいホールでは所作を大きくしないと、後ろのお客さんには見えないよ」と、三代目桂やまと師匠からアドバイスを受けた経験がある。
落語の魅力を尋ねると、「演者により個性が異なるところ」を挙げた。さらに「狭いスペースでどこでも練習できる。一人の方が集中できる。落語は(始めるのに)敷居が低いのではないでしょうか」と続け、身近な話芸であると説明してくれた。

決勝大会に進出した8人(右から2人目が板垣空さん)(写真提供:岐阜市笑いと感動のまちづくり実行委員会)

☆ 擬宝珠(ぎぼし)
板垣空(扇家なん輔)さんが策伝大賞で披露した「擬宝珠」は、寺の屋根のてっぺんや橋の欄干の先にある尖った金属の装飾をなめるのが大好きという風変わりな嗜好(しこう)を持つ主人公の若旦那と、同様に擬宝珠をなめるのが好きな父親(大旦那)の姿や、やり取りを描いた滑稽(こっけい)話。
詳しく書いてしまうと、ネタバレになるので避けるが、板垣さんは、話の本筋はそのままに、「クールでエキサイティング」「金属アレルギー」などの英語も随所にちりばめながら、独自のせりふ、言い回し、登場人物によって「扇家なん輔流」の世界を創出し、客席に大いにアピールした。落ち(結末)の際は会場を大きな拍手と歓声が包んだ。
☆ 板垣空さん
いたがき・そら。神奈川・希望ヶ丘高卒、法学部4年。高座名は、落語研究会の名跡である「扇家なん輔」。中学・高校時代は剣道部に所属。持ちネタは「鷺とり」「犬の目」「親子酒」「擬宝珠」「蚊いくさ」など。蚊いくさは、「蚊と戦う場面が面白く、演じていても楽しい」と笑う。10~15分の持ちネタが多く、30 分以上の演目に比べれば覚える苦労は少ないという。
今は公務員を目指し、勉強に忙しい毎日を送っている。落語会が近づくと、寝る前10分間や、カラオケの個室ですき間時間に練習したりすることもある。2026年の策伝大賞出場については「できるネタがあれば出たい。今はうっすらとネタを探しているところです」と教えてくれた。
☆中央大学落語研究会
1957(昭和32)年創部。関根広大幹事長。部員数は31人(4年生8人、3 年生6人、2年生9人、1年生8人)。落語会を毎年6月、12月に主催している。板垣空さんによると、落研に伝わる名跡は優に100程度はあり、2年生になるとき継承する。新しい名跡を作り、名乗ることもできるそうだ。


第22回全日本学生落語選手権 策伝大賞
全国の62⼤学・⼤学院の308人がエントリー。事前の映像審査と予選を通過した8人が、岐阜市民会館で行われた決勝大会(2025年2月15日)に進んだ。審査の結果、最優秀賞の策伝大賞は京都大の永野泰地さんが受賞。審査員特別賞に京都大の梅原志和さん、岐阜市長賞に二松学舎大の吉田もえさんが輝いた。
決勝出場者は次のとおり(敬称略、名前・大学学年=当時・高座名・演目の順)。
前澤哲人(大阪芸術大3年) 東家四街(あずまや・ぞぞ) 「鈴ヶ森」
吉田もえ(二松学舎大3年) 二松亭姫爆(にしょうてい・きばく) 「現代版厩火事」
野中春菜(福岡大2年) 福々亭兎子(ふくふくてい・うさこ) 「堀の内」
日高 昴(関西学院大4年) 四笑亭丸慧(よんしょうてい・まるふぉい)「お見立て」
加藤優和(青山学院大3年) 燻川木っ葉(いぶしがわ・こっぱ) 「死神・改」
梅原志和(京都大4年) 葵家万羽(あおいや・まんば) 「玉置そば」
板垣 空(中央大3年) 扇家なん輔(おうぎや・なんすけ) 「擬宝珠」
永野泰地(京都大4年) 葵家竹生(あおいや・ちくしょう) 「胡椒のくやみ」
(出演順、策伝大賞ホームページより)
☆ 策伝大賞とは
戦国~江戸期の浄土宗の僧で、さまざまな滑稽話、⼈情話を集めた「醒睡笑(せいすいしょう)」を著し、「落語の祖」といわれる岐阜市出身の安楽庵策伝(あんらくあん・さくでん)。岐⾩市笑いと感動のまちづくり実⾏委員会によると、策伝大賞は、策伝和尚をシンボルキャラクターとして例年2月に開催されている。笑いと感動で街を元気にしようという岐阜市の「笑いと感動のまちづくり事業」のシンボルイベント。⽇本伝統の話芸⽂化、落語の発展と、その担い⼿となる学⽣たちの育成、交流の場になることを⽬指している。主催は、岐⾩市と同実⾏委員会、NHK 岐⾩放送局。

「策伝大賞」決勝大会の映像
第22回全日本学生落語選手権「策伝大賞」決勝大会の映像はこちらからご覧になれます。(岐阜市公式チャンネルより)

板垣空さん(左から2人目)と落語研究会のメンバーたち

策伝大賞決勝大会の会場(岐阜市民会館)
【取材後記】 「なん輔として語ること」 大切にする姿勢が印象的
学生記者 合志瑠夏(経済4)
落語研究会の部室がある多摩キャンパス4号館(サークル棟)には、書道會や竹桐会(和楽器サークル)といった文化系団体の部屋も並んでいて、建物の一角には「和の文化」が息づいているような、静かで落ち着いた空気が漂っていた。
取材で最初に挨拶を交わしたときの板垣空さんの印象は、「柔らかくて控えめな人」。どこかシャイな雰囲気を感じた。しかし、その後、表紙などの写真撮影時に聞かせてくれた声出しや、練習用の高座での堂々とした姿に驚いた。張りのある軽妙な語り口調の板垣さんは着物姿が実に様になっており、生き生きと輝いていた。
「恥ずかしがらずにやることが大切だと思っています」という言葉通り、板垣さんの落語には照れがない。練習では特に「大きく、はっきりとした声を出すこと」を意識しているという。高座での最初の挨拶の時点ですでに発声に気を配っているということから、矜持を感じさせる。
法学部(茗荷谷キャンパス)に在籍する板垣さんは、多摩キャンパスの部室にはめったに来ないそうだが、その分はカラオケボックスや空き時間を利用して自主的に練習しているという。公務員試験の勉強に力を注ぎながら、毎晩寝る前に10分間だけでも落語の練習を続けるというひた向きさに、頭が下がる思いだった。
板垣さんの落語には「自分らしさ」がしっかりと根づいている。オリジナルのせりふや登場人物を積極的に取り入れることで、自分だけの落語を生み出している。演者としての「扇家なん輔」を丁寧に作り上げ、落語家として演じるのではなく、「なん輔として語る」ことを大切にしている姿勢が印象的だった。
落語というと、少し敷居が高いと感じる人も、もしかすると多いかもしれない。実は私自身もその一人だった。しかし、板垣さんの話を聞いて、狭いスペースでも一人で練習でき、演者ごとの個性を楽しめるという自由さや奥深さを知り、ぐっと身近に感じられるようになった。板垣さんにとって、落語はまさに趣味であり、自己表現の場でもあるのだと思う。

【取材後記】 「なん輔流」の世界観を表現 「言葉の演劇」の面白さを知る
学生記者 荒田智海(文2)
声が室内から廊下まで響き渡った。張りのある圧倒的な声量だ。それは表紙の写真撮影で、落語研究会の板垣空さんが演目中と似た動作をカメラマンに求められたときのことだった。その場の空気を支配するような声から、高座での存在感が容易に想像できた。
策伝大賞で披露した「擬宝珠」では、じっと正座して語り続けるのではなく、演目に動きをつけることで、他の演者とは違う落語を見せた。身体全体を使って物語を表現する姿から、落語への情熱を感じられた。加えて、オリジナルのせりふや登場人物を作り出し、「扇家なん輔」の世界観を表現した。
さまざまなネタは、日常生活を送る中で気づいたものから取り入れられ、特に電車に乗っているとき、多くの案が生まれるそうだ。物語を落ち(サゲ)からではなく、初めから展開させていく点も「なん輔流」と言えるかもしれない。
自身の強みには、大きな名乗り声と、落語家ぶらない独自の語り方を挙げた。高座に上がる際には、大きな声であいさつすることを一番に心がけているそうだ。また、一般的な落語家のイメージにあるしっとりとした落ち着いた口調というよりも自身の納得いく語り方を貫いた。これらが組み合わさったことにより、扇家なん輔の落語は、お客を引き付けることにつながったと言えよう。
取材で一番に印象に残った話がある。策伝大賞で一つ前の演者の高座が終わった後のこと。出でばやし囃子が流れたものの、すぐに登場せず、30秒ほど待って高座に出るつもりが、期せずしてお客を約2分、待たせた格好になった。それでも、想定外の事態に動揺することなく、演目をやり終えた姿が格好いい。
さらに、まくら(本編の前の導入部分)で話すのが苦手と教えてくれた。困ったときには、落語研究会に所属する中で出会った先輩や友人に相談し、内容を決めているという。落語を介して親しい関係となった仲間たちは、大学生活に彩りを添える存在になった。
今回の取材をきっかけに、初めて落語を真剣に鑑賞した。自分が知らない世界には、これほどにも面白い「言葉の演劇」があることを知った。まだまだ未知の領域が多いことに歯がゆさも感じるが、触れられる世界がこれほど広いという事実にかえってわくわくする。

落語研究会の板垣空さん(中央)にインタビューした学生記者の合志瑠夏さん(左)と荒田智海さん