- HOME
- Campus Life
- Students Voices 学生インタビュー
- 中央Days! 第4回 理工学部
中央Days!「読売中高生新聞」掲載
- 第4回 理工学部
- 応用化学科
4年 - 馬鳥 沙希さん(22歳)
化学の「ものづくり」を探求
■このコンテンツは読売中高生新聞(2023年1月13日)に掲載された「中央Days!」企画の内容を一部修正して掲出しています。
極小素材 応用展開へ
基礎的な化学の知識を応用して、世の中の役に立つ新しい物質を生み出す力を養う応用化学科。化学の「ものづくり」の学問という側面があり、理工学部の中で女性に人気が高い学科だ。
その中でも馬鳥さんは、生命分子化学という分野で、たんぱく質から作ったバイオマテリアルの研究に取り組んでいる。バイオマテリアルとは生体材料とも呼ばれる、人間の体に移植することを目的に合成した素材のこと。具体的にはマイクロチューブという極めて小さい、長さ18マイクロメートルのチューブ状の素材が研究の対象だ。水の中で自ら動くという性質を利用して、ウイルスをつかまえたり薬物を運んだりといった、主に医療分野への応用をめざしている。
日々の研究では実験が重要になる。マイクロチューブはもちろん肉眼では見えないので電子顕微鏡などを用いるが、そうした高性能の分析機器を使うのは楽しいと馬鳥さんはいう。結果を予測し、そこにいたるプロセスを考えながら進める実験は思い通りにいかないことも多い。そういう時には先生や先輩からアドバイスをもらいながら、何が原因なのかを突きとめて修正し、実験をやり直す。大変な作業に思えるが、「正解があるわけではない。いろいろな結果が出るのはおもしろい」。そういう試行錯誤を楽しむマインドが新たな発見や開発につながるのかもしれない。
理工学部の卒業生の半数が行くという大学院に、馬鳥さんも4月から進む。「今取り組んでいる研究をもっと探究したい」と顔を輝かせる。
HISTORY
社会に役立つ化学 可能性実感
母が薬剤師であることから医学や創薬に関心があり、応用化学科に進学したが、化学が社会でどのように生かされているのかという知識はあまりなかった。大学の授業でこれほど多様な活用法があるのかと学んだ。工場などのパイプに液体を流した時の圧力損失を測る化学工学や、計算だけで結果を予測する計算化学という「フラスコを振るだけではない」化学もあると知り、その学びの奥深さに驚いた。
生命分子化学を主な研究領域とし、大学院でもその道を探究するが、化学という学問の幅の広さに触れて、その後の進路について様々な可能性を思い描く。
Question and Answer
- Q. アルバイトはしている?
- A. 塾講師
個別指導の学習塾で小学生や中学生を教えている。中学受験と大学受験をした経験と知識を生かし、1人ひとりに合った教え方を心がけている。他愛ない会話だが、生徒たちのいろいろな話を聞けるのは楽しい。
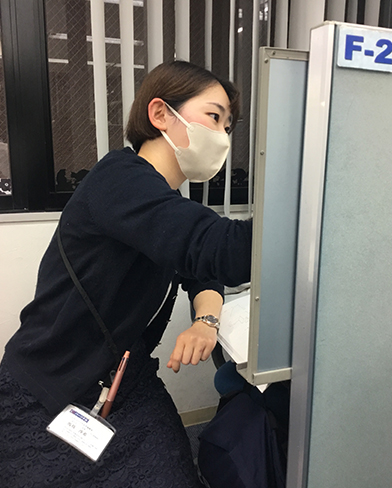
- Q. 学部の“あるある”は?
- A. 東京ドームの音漏れ
理工学部がある後楽園キャンパスから東京ドームは目と鼻の先=写真=。そこでコンサートが開催されている時に、その音が風に乗ってわずかに聞こえてくる。都心のキャンパスならではの雰囲気だろう。

- Q. 学部のおすすめ制度は?
- A. たくみ奨学金
学部独自の海外留学・研修を支援する奨学金。馬鳥さんはオーストラリアに留学した時に利用した。現地の学校=写真=の授業に参加し、様々な国籍や人種の生徒とともに学んだことは、貴重な体験だったと感じている。

-
マストアイテム
大きめの付箋が馬鳥さんが勉強する時の必需品で、ToDoリストとして利用している。その日にしなければいけないことを書いて、終わったら1つずつ消していく。やり残しを防げるうえに、タスクをすべてやり終えた時には達成感がある。

スケジュール
※3年次のもの
| 1 | 化学工学演習 | 習い事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 高分子化学 | |||||
| 3 | 応用化学実験2 | 有機化学3 | 無機化学3 | 応用化学実験4 | アルバイト | |
| 4 | 地学1 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 科学技術と倫理 | |||||
| 授業後 | アルバイト |