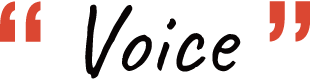FLP
Faculty-Linkage Program
学部の垣根を越えた実践的な学びで
現代の社会で必要な力が身につく。
ファカルティリンケージ・プログラム(FLP)は学部の枠をこえた少人数のゼミで、幅広い学問領域をもつ総合大学のメリットを活かした教育プログラムです。FLP独自に設計された演習科目と各学部に設置された授業科目をピックアップして、5つのプログラムを設定。所属学部で主専攻を修めながら、学部の枠を越えて設けられたプログラムを体系的に学修することで、複数の専門知識をもった学際的な視点を身につけることができます。
1年次後期に選考試験を行い、2年次から3年間のプログラムが開始します。
新たな知識領域を広げる
5つのプログラム
主専攻の学びにプラスして、他分野の高度な専門知識や能力を身につけられるFLPは、中央大学のどの学部の学生でも履修することができます。他学部の学生と一緒に学ぶため、知的な刺激が生まれ、ゼミの仲間たちとの交流を通して、視野や人間関係が広がるのもFLPならではの魅力。以下のような5つのプログラムを設置し、学生の知的興味や好奇心に応えています。
ゼミ形式の学び+実践的な
フィールドワークの学び
FLPの学びの中心となる「演習科目」では、少人数のゼミナール形式で研究を行います。興味のあるテーマの調査・研究を自主的に進めながら、ゼミの仲間とディスカッションをしたり、見学調査や実態調査などのフィールドワークも行います。
卒業単位として認定される
FLPの修得単位
プログラムで修得した講義科目(プログラムによって10~20単位)と演習科目(12単位)の単位は、原則として全て所属学部の単位(卒業単位として認定)になるので、所属学部の学修と両立して無理なく知識を深めることができます。
Program01
環境・社会・ガバナンスプログラム
自然科学と社会科学の視点から
環境問題の解決策を探る。
環境問題を複数の視点から学び、自然と調和しながら社会活動を継続させるために必要な取り組みについて考え、より良い解決策を提起できる能力を養います。
2025年度の演習A 開講テーマ例
環境政策を提言する/環境水の保全と対策
将来の進路
国家公務員・地方公務員をはじめ、建設、運輸、旅行、金融・保険、新聞・放送、メーカーや大学院進学など
Program02
メディア・ジャーナリズムプログラム
デジタル時代のジャーナリストを育てる!
記者、ディレクター・プロデューサー、アナウンサー、編集者、コンテンツ・クリエーターなど、様々なメディアの世界で活躍できる人材を育成します。
2025年度の演習A 開講テーマ例
メディア・ジャーナリズム・ICTの法と倫理/ドキュメンタリー制作およびノンフィクション執筆の実践/“パブリックスピーキング”のスキルと社会を切り取る「視点」を身につける/新聞等の既存メディアからネットメディアまでマスメディアの全体状況を理解すると同時に、事実を正確に伝える文章力を身につける/映像リテラシー・ジャーナリズムとドラマとドキュメンタリー・自分のメッセージ(ドラマ制作)・映像と AI・コミュニケーション力
将来の進路
新聞・放送・出版・広告などのマスメディアのほか、通信、印刷、運輸、メーカー、公務員、大学院進学など
Program03
国際協力プログラム
途上国の開発や格差・貧困に関連する問題の解決法を探る。
開発途上国の諸問題を、経済開発、社会開発(教育、保健・衛生、ジェンダーなど)、環境、国際協力などの多角的な視点から総合的に研究し、格差・貧困問題の解決に貢献できる能力を養います。
2025年度の演習A 開講テーマ例
表面から内面へのまなざしの涵養-国際協力の文脈における「ことばの教育」の視点から/発展途上国の格差・貧困問題と経済・社会開発:学際的・現場重視型アプローチ/企業・産業の国際比較~グローバル思考養成のために/〈ひとのつながりの新たなかたち〉を構想する惑星社会のフィールドワーク/開発社会学を通して東南アジアを捉える/変わりゆく世界と新たな国際協力のありかた/日本のODAから地方創生への環流:実務的アプローチ
将来の進路
国連や JICAといった途上国開発関連の機関をはじめ、JICA 海外協力隊、国際協力 NGOs、商社、メーカー、金融機関、コンサルタント会社(開発、経営)、放送・新聞業界、国家公務員(外務省含む)、教員、国内外の開発系大学院進学など
Program04
スポーツ・健康科学プログラム
スポーツで社会を変える人材の育成を目指す。
スポーツを健康、医療、文化、ビジネス、サービス、行政などとの関連の中で多面的に理解し、幅広い分野でスポーツの発展に寄与できる能力を養います。
2025年度の演習A 開講テーマ例
スポーツ心理(認知・行動)部分を知る/日本における競技スポーツ文化を考える/剣道を通じたビジネスおよび海外文化の理解/パフォーマンスの測定・分析/スポーツを通じた国際協力の理論と実践/スポーツによる地域活性化の可能性に関する研究
将来の進路
スポーツ産業界(Jリーグ、球団、スポーツメーカー、広告代理店、介護ビジネス)をはじめ、各スポーツ機関(日本アンチドーピング機構、日本陸上競技連盟など)、行政機関(各自治体職員)や教育機関(大学職員等)、大学院への進学など
Program05
地域・公共マネジメントプログラム
地域の課題を直視し、ニーズに応え、豊かな暮らしを構想する。
様々な課題を抱える地方自治体の要望に応えられるよう、専門的な知識やスキルを習得。地域社会で、課題解決の政策形成を担える能力を養います。
2025年度の演習A 開講テーマ例
地域資源を活かした地域経営を考える:そのための地域資源の再発見・再評価、マネジメント/地域創生のデザインと地域イノベーション/地域活性化の源泉を探る/現代日本社会において人びとが生きていく場所としての地域を考える/地域に寄りそい、ひとにこころを寄せるフィールドワークと子どもたちが「生きやすい」コミュニティづくり/地域計画のための分析手法/スポーツによる地域活性化の可能性に関する研究/「大学は社会のために何ができるか」を考える
将来の進路
多くの国家公務員・地方公務員をはじめ、電気、建設、不動産、金融・保険や大学院進学など
メディア・ジャーナリズムプログラム
総合大学ならではの学部の枠をこえた学び
川嶋 佳恋国際情報学部 国際情報学科 2年 神奈川県立希望ケ丘高等学校出身※2024年度の取材時点における学年となります。

- プロの方から学んだり、色々なことを積極的に吸収しています。
-
高校時代からテレビドラマなどが好きなのもあって、メディア系の方面に進めればと思っていました。FLPについては入学オリエンテーション説明会のときに知り、学部横断というところに興味を惹かれました。
そこにちょうどメディア・ジャーナリズムプログラムがあるということで、受講を決めました。現在は、夏に宮城県女川町へ取材をさせていただいたニュース番組の映像制作に取り組んでいます。
パブリックスピーキングを学び、現地取材を行い、映像編集をして……と楽しみながら勉強ができています。
その中で言葉で伝えることの大切さやその際に意識すべきポイント、物事を捉える力も身につきました。